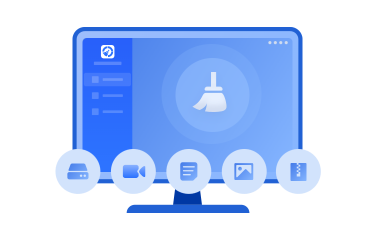Cleanmgrコマンド完全ガイド|Windowsのディスククリーンアップを行う方法
Windowsを使用していると避けられないのが、日々増えていく「不要ファイル」や「一時ファイル」の問題です。PCの動作が遅い、ストレージの空きが少ないと感じたら、まず試すべきは「ディスククリーンアップ」です。今回は、Windowsに標準で搭載されている「Cleanmgr(ディスククリーンアップ)」コマンドの使い方をわかりやすく説明します。
Cleanmgrとは?
Cleanmgr(クリーンマネージャー)は、Windowsに標準搭載されているディスククリーンアップツールのコマンド版です。GUIでの「ディスククリーンアップ」と同様に、不要な一時ファイル、システムキャッシュ、Windows Updateの残骸などを削除してディスク容量を回復できます。cleanmgr.exeとして存在し、バッチ処理や自動化に利用しやすいのが大きな利点です。
Windowsの「Cleanmgr」コマンドは、長年にわたり多くのユーザーに愛用されてきたディスククリーンアップツールです。 GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)でおなじみの「ディスククリーンアップ」をコマンドラインから自動で実行できるのが大きな特徴です。 これにより、手動でのクリック操作を繰り返すことなく、不要なファイルを一括で定期的に削除できるのが便利です。 Cleanmgrは特にWindows 10まで利用されてきましたが、Windows 11以降では使用が制限されることもあるため、代替手段を知っておくと安心です。
Cleanmgrコマンドの基本的な使い方
Cleanmgrのコマンド操作には、基本的に2つのステップがあります。1つ目は削除対象を指定するための「sageset」、2つ目は実際に削除を実行する「sagerun」です。
-
コマンドプロンプトを管理者として起動します。
-
「cleanmgr」と入力し、Enterキーを押します。
-
クリーンアップするドライブを選択します。
-
削除したいファイルの種類を選択し、「OK」をクリックします。
ステップ①:Cleanmgrの設定を記憶させる(sageset)
まずは削除したいファイルの種類を一度だけ指定して記憶させます。
cleanmgr /sageset:1
このコマンドを実行すると、GUIの「ディスククリーンアップのオプション選択画面」が開きます。ここで削除したいファイル項目(例:一時ファイル、サムネイル、システムエラーメモリダンプなど)を選びます。番号「1」は設定のIDで、任意の数値に変更可能です(例:2、10など)。
ステップ②:記憶した設定で実行する(sagerun)
次に、記憶した設定に基づいて削除を実行します。
cleanmgr /sagerun:1
これで、先ほどsageset:1で保存した項目が自動的に削除されます。タスクスケジューラーと組み合わせれば、毎週・毎月など定期的なクリーンアップも自動化可能です。
- Cleanmgrコマンドのオプション:
- /d ドライブ文字:クリーンアップするドライブを指定します。例:/d c:
- /sageset:n:ディスククリーンアップの設定を保存します。nは設定を識別する番号です(0から65535までの任意の整数)。
- /sagerun:n:保存された設定を読み込んでディスククリーンアップを実行します。nは`/sageset`で指定した番号と同じ値を指定します。
- /lowdisk:ディスク容量が少ない場合に、デフォルトの設定でディスククリーンアップを実行します。
- /verylowdisk:ディスク容量が非常に少ない場合に、ユーザープロンプトなしでデフォルトの設定でディスククリーンアップを実行します。
- /autoclean:Windowsのアップグレード後に残されたファイルを自動的に削除します。
▼例
- Cドライブのディスククリーンアップをデフォルトの設定で実行する場合:cleanmgr /d c:
- ディスククリーンアップの設定を保存する場合(例:番号10に保存):cleanmgr /sageset:10
- 保存した設定(番号10)でディスククリーンアップを実行する場合:cleanmgr /sagerun:10
● /sagesetで設定を保存する際には、削除したいファイルの種類を選択する必要があります。
● /sagerunで実行する際には、/sagesetで保存した設定と同じ番号を指定する必要があります。
● ディスククリーンアップで誤って重要なファイルを削除しないように注意してください。
(☞゚ヮ゚)☞参考出典はこちら:Microsoft Ignite
Cleanmgrコマンドで削除できる主なファイル一覧
Cleanmgrで削除できる代表的なファイルには以下のようなものがあります:
- 一時ファイル(Temporary Files)
- サムネイルキャッシュ
- Windows Updateの一時ファイル・残骸
- ごみ箱の中身
- 古いシステムの復元ファイル(Service Pack Backup)
- Internet Explorerのキャッシュや履歴
- ログファイルやエラーレポート
- Microsoft Defenderによるスキャン履歴
これらの中には数GB単位の容量を使っているものもあるため、定期的な削除が効果的です。
Partition Assistant for Cleanupでさらに深く削除する方法
Cleanmgrは便利ですが、削除対象はあくまでWindowsが定めた「安全な範囲」に限られます。もっと詳細なクリーンアップをしたい場合は、Partition Assistant for Cleanupのようなサードパーティ製ツールが有効です。
このツールは、Windows 11/10/8/7/Serverなどに対応した無料で使えるモダンなPCクリーンアップソフトで、Cleanmgrの代替としても最適です。
Partition Assistant for Cleanupを使えば:
- ジャンクファイル(.log, .tmp など)を高速スキャン&削除
- GB級の大容量ファイルを可視化して削除
- 重複ファイルをスキャンし、無駄なコピーを削除
- クリーンアップ前にファイル内容を確認可能
Cleanmgrでは対象外の、ユーザーフォルダ内の一時ファイルや、長年放置された古いインストーラー・キャッシュ類まで徹底的に整理できるのが魅力です。
ステップ 1. Partition Assistant for Cleanupをインストールして起動します。「ジャンクファイルの削除」タブをクリックします。「スキャン開始」ボタンをクリックして、ジャンクファイルのスキャンを開始します。
ステップ 2. スキャン処理が完了すると、すべてのシステムジャンクファイル(ごみ箱ファイル、一時ファイル、ログファイル、無効なショートカットなど)とレジストリジャンクファイル(DLLレジストリ、システムレジストリ、プログラムレジストリなど)が表示されます。不要なファイルを選択したら、「今すぐ削除」ボタンをクリックしてクリーンアップを開始します。
ステップ 3. クリーンアップには時間がかかる場合があります。選択したファイルがクリーンアップされます。プロセスが完了すると、クリーンアップ完了ウィンドウが表示され、クリーンアップ済みのファイルとまだクリーンアップされていないファイルの数が表示されます。
Windows11でCleanmgrが使えない場合の代替策
Windows 11では、MicrosoftがCleanmgrの非推奨を進めており、環境によっては正常に動作しないケースがあります。以下のような代替手段を活用すると良いでしょう:
1. ストレージセンサーを利用
ステップ 1. 「スタート」アイコン→「設定」をクリックします。
ステップ 2. 「システム」→「記憶域」をクリックします。
ステップ 3. 「ストレージセンサー」のスイッチをオンにします。
ステップ 4. 詳細設定で「毎週削除」「30日以上の一時ファイルを削除」などを指定可能です。
2. PowerShellスクリプトで削除
PowerShellのRemove-Itemコマンドを使えば、対象フォルダを指定して削除できます。
ステップ 1. スタートメニューで「PowerShell」と検索、「Windows PowerShell(管理者として実行)」を右クリックして起動します。
ステップ 2. Cleanmgrの代替として、以下のようなPowerShellスクリプトもおすすめです:
Remove-Item -Path "$env:TEMP\*" -Force -Recurse
ステップ 3. また、以下を使えばブラウザキャッシュやログファイルのクリーンアップも可能です:
Get-ChildItem -Path "C:\Users\YourUserName\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache" -Recurse | Remove-Item -Force
PowerShellは高度ですが、使い慣れればより細かく、正確に不要ファイルを処理できます。
3. Partition Assistant for Cleanupを使う
GUIでわかりやすく、しかも強力に不要ファイルをスキャン・削除できるため、Cleanmgrの代替として最適です。
結論
Cleanmgrは、Windowsに標準で搭載されているシンプルでありながら強力なディスククリーンアップツールです。 コマンドラインから実行することで、不要なファイルを効率的に削除でき、定期的に実行することも可能でメンテナンス性が向上します。 しかし、Windows 11では一部制限があるため、ストレージセンサーやPowerShell、さらにはPartition Assistant for Cleanupなどの代替手段を併用するのが現代的な方法です。 不要なファイルを継続的に整理することで、PCの動作が軽快になり、トラブルの予防にもつながるでしょう。
よくある質問
1. Cleanmgrコマンドの基本的な使い方は?
基本的な使い方は「cleanmgr」と入力するだけでディスククリーンアップのGUIが起動します。また、「cleanmgr /d C:」とすれば、Cドライブを対象に処理が開始されます。指定しない場合は、OSがインストールされているドライブが自動的に選ばれます。
2. Cleanmgrの/sagesetと/sagerunの違いは?
「/sageset」はクリーンアップのオプション(どの種類のファイルを削除するか)をあらかじめ設定して保存するためのスイッチで、「/sagerun」はその設定を呼び出して実際にクリーンアップを実行するためのものです。たとえば、「cleanmgr /sageset:1」で設定した後、「cleanmgr /sagerun:1」を実行することで、指定した項目だけを自動的に削除できます。
3. Cleanmgrの実行後に再起動は必要ですか?
通常のクリーンアップでは再起動は必要ありませんが、システムファイルやWindows Updateのキャッシュなど一部の項目を削除した場合は、再起動が必要になることがあります。また、「以前のWindowsのインストール」などを削除する際には、再起動が促されることがあります。