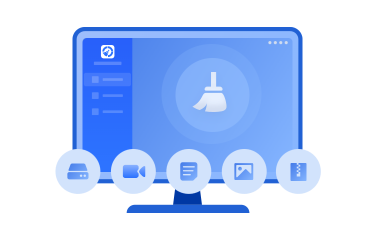HDDの読み込み・書き込み速度が遅くなる原因と解決方法
本記事では、HDDの読み込み・書き込み速度が遅くなる原因と、その対策をステップごとに詳しく解説します。「最近パソコンが遅い」と感じている方は参考にしてください。
HDDの基本構造と仕組みを理解する
HDDの速度低下を理解するには、まずその構造と仕組みを知ることが大切です。
HDDの内部には「プラッター」と呼ばれる円盤がいくつかあり、その表面にデータが磁気的に記録されています。このプラッターを高速で回転させ、読み書き用の「ヘッド」が必要な位置に移動してデータを読み取ります。回転数(RPM)が高いほど、読み書きの速度は速くなりますが、その分発熱や摩耗のリスクも増加します。
HDDでデータを読み書きする時、プラッターが物理的に回転し、ヘッドが正しい位置に移動する必要があります。これが機械的な動作なので、SSDのような半導体メモリ方式に比べて遅くなりがちです。さらに、断片化が進むと、ヘッドが頻繁に別の位置に移動するため、速度が低下します。
SSDは可動部品がなく、ランダムアクセス速度が非常に速いため、OSやアプリの起動が圧倒的に早いです。一方、HDDは大容量・低価格が魅力ですが、速度ではSSDに大きく劣ります。特に、経年劣化したHDDは新品SSDの10分の1以下の速度になることもあります。
HDDが遅くなる主な原因
HDDが遅くなる原因は一つではありません。主に以下のような要因が考えられます。
①物理的な劣化(経年劣化や摩耗)
HDDは物理的な部品で構成されているため、使えば使うほど摩耗や劣化が進みます。特にプラッターやヘッドは精密機械であり、微細な損傷でも性能の低下を引き起こす可能性があります。一般的に、HDDの寿命は3〜5年とされています。
②フラグメンテーション(断片化)の影響
ファイルが分割されて異なる場所に保存される「断片化」が進むと、ヘッドの移動回数が増え、読み書き速度が落ちます。特にWindowsでは長期間使っていると断片化が進みやすいです。
③不要なバックグラウンドプロセス
常駐ソフトやバックグラウンドで動作しているアプリケーションがHDDを頻繁にアクセスすると、他の処理が遅くなります。特にクラウド同期や自動アップデートが原因となることがあります。
④ウイルスやマルウェア感染
悪意のあるプログラムがHDDに頻繁にアクセスし、リソースを奪うことで速度が低下することがあります。セキュリティソフトによる定期的なスキャンが必要です。
HDDの読み込み・書き込み速度が遅くなる場合の対処法
HDDは長期間の使用や容量不足、断片化、物理的劣化などにより速度が低下します。 放置すると起動やファイルの読み書きが遅くなるため、以下の方法で改善を試してみましょう。
1. 不要ファイル・アプリの削除
長く使用しているHDDは、データの断片化や不要ファイルの蓄積、ストレージの空き容量不足などが原因で、読み込みや書き込み速度が遅くなることがあります。特に大容量のファイルを扱う場合や、OSやアプリの起動が遅くなったと感じる場合は、ストレージの整理が必要です。こうした状況で役立つのがPartition Assistant for Cleanupです。このソフトは、HDD内の不要ファイルや一時ファイルをスキャン・削除し、ストレージの最適化を行うことで、読み込みや書き込みの速度改善をサポートします。
Partition Assistant for Cleanupは、HDDの不要データを短時間で検出でき、シンプルな操作で安全に削除できます。特に、キャッシュや古いログファイル、重複ファイル、大容量で使われていないデータなどを一括で整理できるため、ディスクの負担を軽減し、パフォーマンスの回復につながります。
ステップ 1. Partition Assistant for Cleanupをインストールして起動します。「ジャンクファイルの削除」タブをクリックします。「スキャン開始」ボタンをクリックして、ジャンクファイルのスキャンを開始します。
ステップ 2. スキャン処理が完了すると、すべてのシステムジャンクファイル(ごみ箱ファイル、一時ファイル、ログファイル、無効なショートカットなど)とレジストリジャンクファイル(DLLレジストリ、システムレジストリ、プログラムレジストリなど)が表示されます。不要なファイルを選択したら、「今すぐ削除」ボタンをクリックしてクリーンアップを開始します。
ステップ 3. クリーンアップには時間がかかる場合があります。選択したファイルがクリーンアップされます。プロセスが完了すると、クリーンアップ完了ウィンドウが表示され、クリーンアップ済みのファイルとまだクリーンアップされていないファイルの数が表示されます。
Windows標準ツールで使っていないソフトや不要ファイルを削除することで、HDDの空き容量を確保できます。空き容量が少ないとパフォーマンスが落ちるため、最低でも全体の15%は空けておくのが理想です。
▶ ディスククリーンアップ
ステップ 1. スタートメニューで「ディスククリーンアップ」と検索して起動します。
ステップ 2. 対象のドライブ(通常はC:)を選択し、「OK」をクリックします。
ステップ 3. 「一時ファイル」「縮小表示(サムネイル)」「ごみ箱」などにチェックを入れて、「OK」をクリックしてクリーンアップが開始されます。
▶ 不要アプリをアンインストール
ステップ 1. 「設定」→「アプリ」→「アプリと機能」を開きます。
ステップ 2. 使用していないアプリを一覧から探します。
ステップ 3. 対象のアプリをクリックし、「アンインストール」を選びます。
2. デフラグによる断片化の解消
Windowsには「ドライブのデフラグと最適化」という機能があります。これを使うと断片化を解消し、ファイルを連続的に並べ直してHDDの読み込み速度を改善できます。※SSDではデフラグ不要なのでHDDのみ実行してください。
(☞゚ヮ゚)☞関連記事:Windows 10/11でハードディスクを最適化する方法
ステップ 1. スタートメニューから「ドライブのデフラグと最適化」を検索して開きます。または、「Windowsシステムツール」→「ドライブのデフラグと最適化」と辿ります。
ステップ 2. ドライブの一覧から、最適化したいHDDを選択します。
ステップ 3. 「最適化」ボタンをクリックします。最適化が完了するまで待ちます。
3. SATAケーブル・ポートの交換
HDDが正常に動作しているのに速度が遅い場合、接続しているSATAケーブルやポートに問題があるかもしれません。 ケーブルが劣化していたり、接触不良があると、転送速度が落ちます。 また、マザーボードのSATAポートには世代があり、古いSATA2(最大3Gbps)よりもSATA3(最大6Gbps)の方が速いです。 古いケーブルやポートを最新の規格に変えるだけで、転送速度がほぼ倍になることもあります。
ステップ 1. 完全にシャットダウンし、電源ケーブルを抜きます。
ステップ 2. HDDとマザーボードをつなぐSATAケーブルを新品に交換、または別ポートに接続します。
4. ファイルシステムのエラーチェック
ファイルシステムにエラーが発生していると、HDDの読み込み・書き込み速度に影響が出ることがあります。ファイルシステムにエラーがないか確認し、必要であれば修復しましょう。
ステップ 1. まず、WindowsキーとRキーを同時に押し、「ファイル名を指定して実行」に「cmd」と入力し、「Enter」を押してコマンドプロンプト(CMD)を起動します。
ステップ 2. 次のコマンドを入力してEnterキーを押します(※ドライブ文字はHDDに割り当てられたものに置き換えてください):
👉chkdsk E: /f /r
-
/f:ファイルシステムエラーの修復
-
/r:不良セクタのスキャンと回復
ステップ 3. スキャンが完了するまで待ち、表示された内容に従って対処します。
上述の方法はHDDエラーチェックに十分ですが、一部のユーザーは、CHKDSKが10%で停止するエラー、やWindows 10でドライブのスキャン、修復が進まないエラーに遭ったことがあるでしょう。こういう時、専門的なサードパーティ製のツールを使ってHDDエラーをチェックできます。弊社のパーティション管理ソフトであるPartition Assistant for Managementはで、パーティションとディスク両方をチェックできます。
Partition Assistant for Managementを起動します。チェックしたいドライブを右クリックし、「詳細処理」⇒「パーティションをチェック」を選択します。ポップアップにエラーチェックのみ、エラーチェックと修復、不良セクタチェック、3つのオプションがあります。必要に応じて一つを選択してください。
5. ウイルス対策ソフトの実行
ウイルスやマルウェアに感染すると、システムの動作が遅くなることがあります。ウイルス対策ソフトでスキャンし、感染している場合は駆除しましょう。
ステップ 1. スタートをクリックし、メニューから「Windowsセキュリティ」を選択します。
ステップ 2. Windowsセキュリティ画面で、「ウイルスと脅威の防止」をクリックします。
ステップ 3. 右ペインで「クイックスキャン」をクリックします。
ステップ 4. 脅威が検出された場合は、指示に従って駆除します。
6. SSDへの移行
最も効果的な高速化の方法は、HDDからSSDに移行することです。 SSDは可動部品がなく、アクセス速度がHDDの数倍から数十倍速いです。 特にOSやアプリケーションをSSDにインストールすると、起動時間や読み込み時間が大幅に短縮されます。 HDDはデータ保存用、SSDは起動ディスクとして使う「デュアル構成」もおすすめです。
ステップ 1. Partition Assistant for Managementをダウンロード、インストール、起動します。クローン先のディスクを右クリックして、「ディスクをクローン」を選択します。
ステップ 2. クローン先のディスクを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
ステップ 3. 確認画面に移動して、クローン元のディスクとクローン先のディスクを確認します。問題なければ「確認」ボタンをクリックして、続行します。「設定」をクリックして、ターゲットディスク上のパーティションを編集することができます。
ステップ 4. 「適用」⇒「続行」をクリックして、この操作を実行します。
7. 外付けHDDの活用
外付けHDDはバックアップ用途だけでなく、データの一時保管や移動にも便利です。ただし、USB接続の場合は規格によって速度が大きく異なります。USB2.0よりもUSB3.0、可能ならUSB3.1やUSB-C対応のものを使うと良いでしょう。また、外付けHDDを頻繁に使う場合は、放熱対策も忘れずに行うことが重要です。
まとめ
HDDの読み込みや書き込み速度低下は、物理的な劣化だけでなく、容量不足やファイルの断片化、ケーブルやポートの不良など、さまざまな要因で発生します。まずは不要ファイル削除やデフラグ、ケーブル交換などの基本的な対策を試し、それでも改善しない場合はSSDへの換装を検討するとよいでしょう。定期的なメンテナンスがHDDの長寿命化と快適なPC動作につながります。
よくある質問
1. HDDが突然遅くなるのはなぜ?
HDDが突然遅くなる原因には、断片化の急激な進行、不良セクタの発生、ウイルス感染、ケーブルやポートの不良などがあります。特に、物理的な損傷や寿命が近い場合は、急激に性能が低下することがあります。このような場合は、まずバックアップを取り、SMART情報を確認して早急に対応しましょう。
2. HDDとSSD、どちらにすべき?
速度を重視するならSSD、容量単価を重視するならHDDです。理想はOSやアプリをSSDに、動画や写真などの大容量データをHDDに保存する「ハイブリッド構成」です。これにより、速度とコストパフォーマンスの両立が可能になります。
3. HDDの寿命はどれくらい?
一般的に3〜5年が目安ですが、使用環境や稼働時間によって大きく変わります。高温・高負荷状態で使い続けると寿命は短くなりますが、低温・安定稼働であれば5年以上使えることもあります。
4. データ復旧は可能?
論理障害(ファイルシステム破損など)の場合はソフトで復旧できることがありますが、物理障害(ヘッド損傷など)の場合は専門業者に依頼する必要があります。ただし費用は高額になりがちなので、日常的なバックアップが一番の予防策です。
5. HDDを長持ちさせる方法は?
温度管理、衝撃防止、定期的な健康診断、不要ファイルの削除、そして適切な電源管理が重要です。また、使用頻度が低いHDDは完全に電源を切って保管することで劣化を遅らせられます。